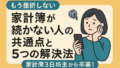【保存版】子育て世帯がやるべき節税5選|知らないと損する制度とは?

✅ 子育て中だけど、お金がどんどん出ていく…
✅ 節約は頑張ってるのに、なかなか貯金が増えない
✅ 「控除」や「制度」って難しそうでスルーしてた…
そんな方にこそ知ってほしいのが、“国が用意してくれている節税制度”の活用法です。
私はFPとして1000世帯以上の家計相談を行ってきましたが、
驚くほど多くのご家庭が「本来なら減らせる税金」をそのまま払い続けていました。
このブログでは、
✅ 確定申告いらずで誰でも使える制度
✅ 子育て世帯だからこそ最大限使える控除
✅ お金を「貯めながら減税」できる仕組み
を【5つの具体策】として、わかりやすく解説します!
✅まず結論|節税=「使える制度を知ること」
節税とは、何か裏ワザを使うことではなく、
「正当な制度を、正しく活用すること」です。
せっかくある正当な制度を使わないなんてもったいない。
👨👩👧子育て世帯は“控除・減税・給付”のチャンスが豊富!
- 児童手当や扶養控除
- 医療費控除や生命保険料控除
- NISAやiDeCoなどの税制優遇制度
知らずに放置すれば、数十万円単位で損している可能性も!
💸子育て世帯がやるべき節税術①|配偶者控除・扶養控除の最適化
🔍チェックポイント:
・配偶者(主に妻)の年収が103万円 or 130万円を超えていないか?
・お子さんが16歳以上の場合、扶養控除の申請をしているか?
✅配偶者控除の基本
| 配偶者の年収 | 控除額 | 備考 |
|---|---|---|
| ~103万円 | 最大38万円 | 所得税&住民税で減税効果あり |
| ~150万円 | 配偶者“特別”控除が段階的に適用 |
📌年収130万円以上で社会保険加入が必要になる場合もあるので、共働き家庭は特に注意!
🏥子育て世帯がやるべき節税術②|医療費控除の活用
✅対象となる支出:
・家族全員の医療費の合算
・通院交通費(公共交通機関)
・出産費用・不妊治療・歯科矯正(条件あり)
✅控除の計算式
医療費控除額 = 実際に支払った額 - 保険等で補填された額 - 10万円(※)
※総所得が200万円未満の人は「所得の5%」
✅実際の控除額例(年収500万円世帯)
- 医療費:年間30万円(家族4人分)
- 保険で補填された分:5万円
→ 控除対象:25万円−10万円=15万円
→ 所得税+住民税で約3〜5万円の節税効果!
🏠子育て世帯がやるべき節税術③|住宅ローン控除のフル活用
「マイホームを買った人」は絶対に活用すべき!
✅住宅ローン控除とは?
・住宅ローン残高の0.7%(最大13年間)が所得税・住民税から控除される制度
・年末の残高に応じて毎年10万円前後の減税が見込める
✅注意ポイント
- 初年度は「確定申告」が必須
- 2年目以降は「年末調整」でOK
- フラット35や民間ローンでも利用可能
💡夫婦ペアローンでも、各人の所得に応じて控除が別々に適用されます!
📈子育て世帯がやるべき節税術④|iDeCoで老後資金と節税を同時に!
✅iDeCoの魅力は“3重の節税効果”
| 節税ポイント | 内容 |
|---|---|
| ① 掛金が全額所得控除 | 所得税・住民税が軽減される |
| ② 運用益が非課税 | 利益に税金がかからない |
| ③ 受け取り時も控除適用 | 一時金・年金受取時に税制優遇がある |
✅子育て世帯へのおすすめ理由
- 月5000円〜OK → 家計に負担なく続けられる
- 「教育費」「住宅費」など他の支出とバランスを取りながら積立可能
- 専業主婦でも加入できる!(※2022年制度改正後)
🎁子育て世帯がやるべき節税術⑤|ふるさと納税で実質2000円の節税ギフト
もはや節税&節約の定番!
✅ふるさと納税の基本ルール
・自分の「住民税+所得税」から控除される
・自己負担は実質2,000円
・寄附した自治体から“返礼品”がもらえる(米・肉・日用品など)
✅子育て世帯向け!おすすめ返礼品
- おむつ・ミルク・離乳食セット
- 冷凍惣菜や子どもが喜ぶフルーツ・お肉
- ランドセルや学用品(※一部自治体)
📌申請は「ワンストップ特例制度」で超カンタン!
✅まとめ|子育て世帯が使うべき“5大節税制度”一覧
cssコピーする編集する① 配偶者控除・扶養控除 → 共働きや子どもの年齢で調整を
② 医療費控除 → 年間10万円以上なら申告を忘れずに
③ 住宅ローン控除 → 初年度は確定申告を!
④ iDeCo → 月5,000円〜で将来と税金をWで守る
⑤ ふるさと納税 → 返礼品を生活費に活用&節税
✨最後に|節税は“ズル”ではなく“正しい戦略”
いかがでしたか?税金を抑えることは、国の制度を正しく活用して、家計にゆとりを生むこと。
🏡 子育てには「教育費・住宅費・食費」と多くのお金がかかります
💰 だからこそ、使える制度は“全部使い倒す”くらいでちょうどいい!
🌱 明日の支出を減らすより、今日から使える制度を活かしましょう!