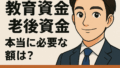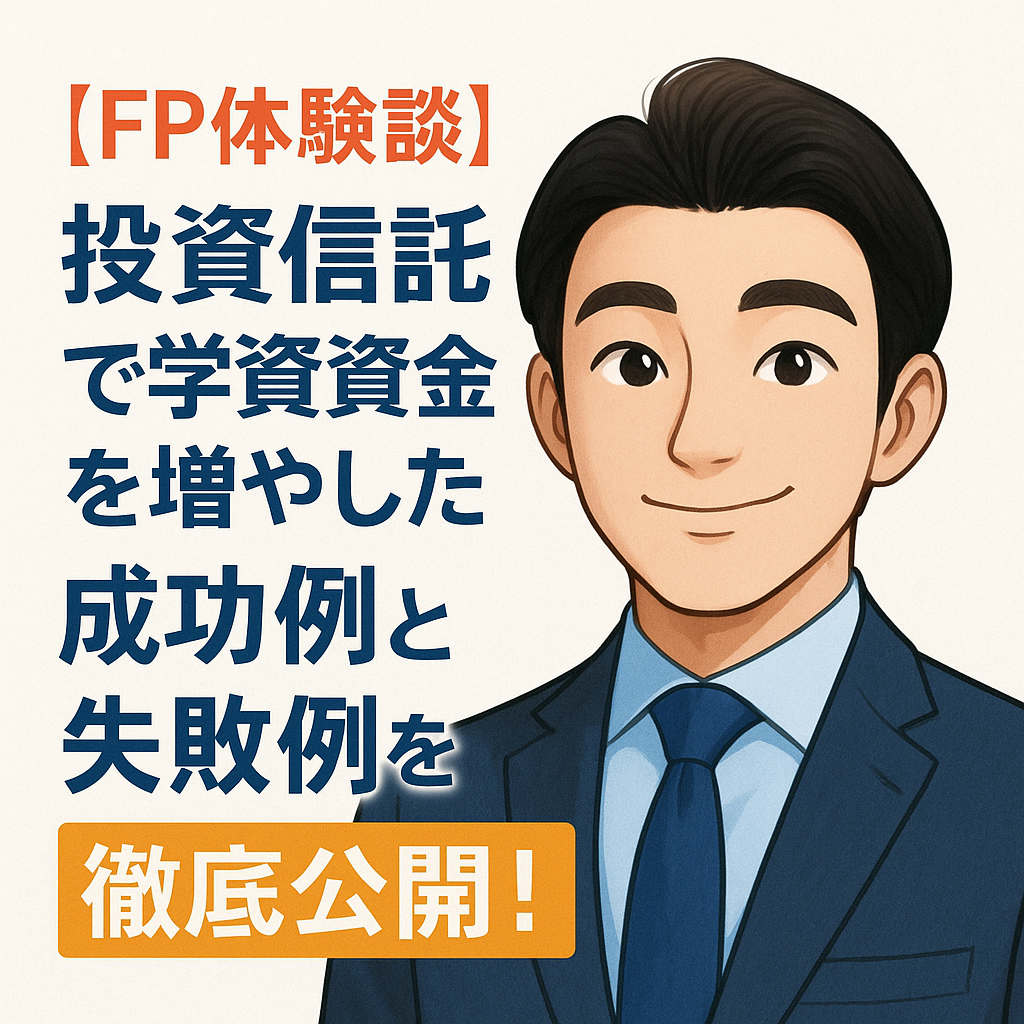
「学資保険じゃ増えない…」「預金だけで教育費が足りるのか不安…」
そんな悩みを持つ子育て世帯に注目されているのが、投資信託による学資資金づくりです。
しかし、実際には「うまくいった家庭」と「途中で失敗した家庭」が分かれるのも事実。
本記事では、ファイナンシャルプランナー(FP)として1,000世帯以上の家計を見てきた筆者が、実際の成功例・失敗例・シミュレーションを交えてリアルな声をお届けします。
このブログでわかること
- 学資資金を投資信託で貯めた実例とその成果
- うまくいかなかった失敗パターンと回避策
- FP視点で考える「投資×学資」の適切な運用方法
- 年齢別・金額別のおすすめ運用シミュレーション
🎯 目的は「教育費の備えをインフレに負けずに準備する」こと
学資保険や定期預金も悪くはありませんが、インフレや金利の上昇に追いつかない可能性が高いです。
そのため、つみたてNISAなどの投資信託で、“時間を味方にする”資産形成が注目されています。
ただし、教育費という「使う時期が決まっているお金」だからこそ、戦略的な運用が求められます。
✅ 成功例①:月3万円×10年で学費をしっかり準備(実例)
プロフィール
- 世帯年収:800万円
- 子ども:小1のタイミングで運用スタート
- 運用方法:つみたてNISA(月3万円)+特定口座(月1万円)
結果
- 運用期間:10年
- 利回り平均:約4.2%
- 最終金額:約500万円(元本:360万円)
▶ 小学校〜高校までの学費+入学準備金に充当できた
成功のポイント
- 「長期・積立・分散」の原則を守った
- リスク許容度を年1回見直した
- 「18歳になるまで引き出さない」と決めていた
❌ 失敗例①:ジュニアNISAでリスクを取りすぎたケース
プロフィール
- 世帯年収:600万円
- 子ども:0歳からジュニアNISAで運用
- 運用方法:米国個別株&テーマ型投信を選択
結果
- 運用期間:8年
- 利回り:−12%(タイミングによる暴落)
- 最終金額:約220万円(元本:250万円)
▶ 高校入学の時期と重なり、予定の金額に届かず
失敗の原因
- 短期的な値上がり益を狙った個別株運用
- 途中で一時売却→タイミングを見誤った
- 「いつ使うお金か」の設計が曖昧だった
📊 FPおすすめの資金設計シミュレーション(年齢別)
| 子どもの年齢 | 準備期間 | 月額投資額 | 利回り3%想定での総額 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 18年 | 月2万円 | 約530万円 |
| 5歳 | 13年 | 月3万円 | 約600万円 |
| 10歳 | 8年 | 月4万円 | 約440万円 |
▶ ポイントは「早く始めるほど、毎月の負担が少なく済む」
💡 FP視点で考える!投資信託で学資資金を増やすポイント
- ①「いつ必要か」を逆算してリスク設計
- ② ジュニアNISAよりも“親名義のつみたてNISA”のほうが柔軟
- ③ 教育費の「出口戦略」が超重要(18歳前から徐々にリスク資産を現金化)
- ④ 増やすだけでなく「減らさない」仕組みを(分散投資・長期積立)
🔚 まとめ|学資は「預金」だけでは足りない時代
投資信託を活用した学資資金づくりは、FPとしても非常に効果的な手段だと感じています。
ただし、成功には「ルールの徹底」と「冷静な戦略」が欠かせません。
✅ 教育費=“いつまでに必要か”が明確な資金 ✅ 投資信託=“時間をかけて増やす”道具
この2つの性質を理解し、目的に合った運用を行うことで、将来の教育費不安は大きく減らせます。
今の時代、「投資=怖い」は思い込みです。 正しい知識と戦略で、子どもの未来を一緒に守っていきましょう。