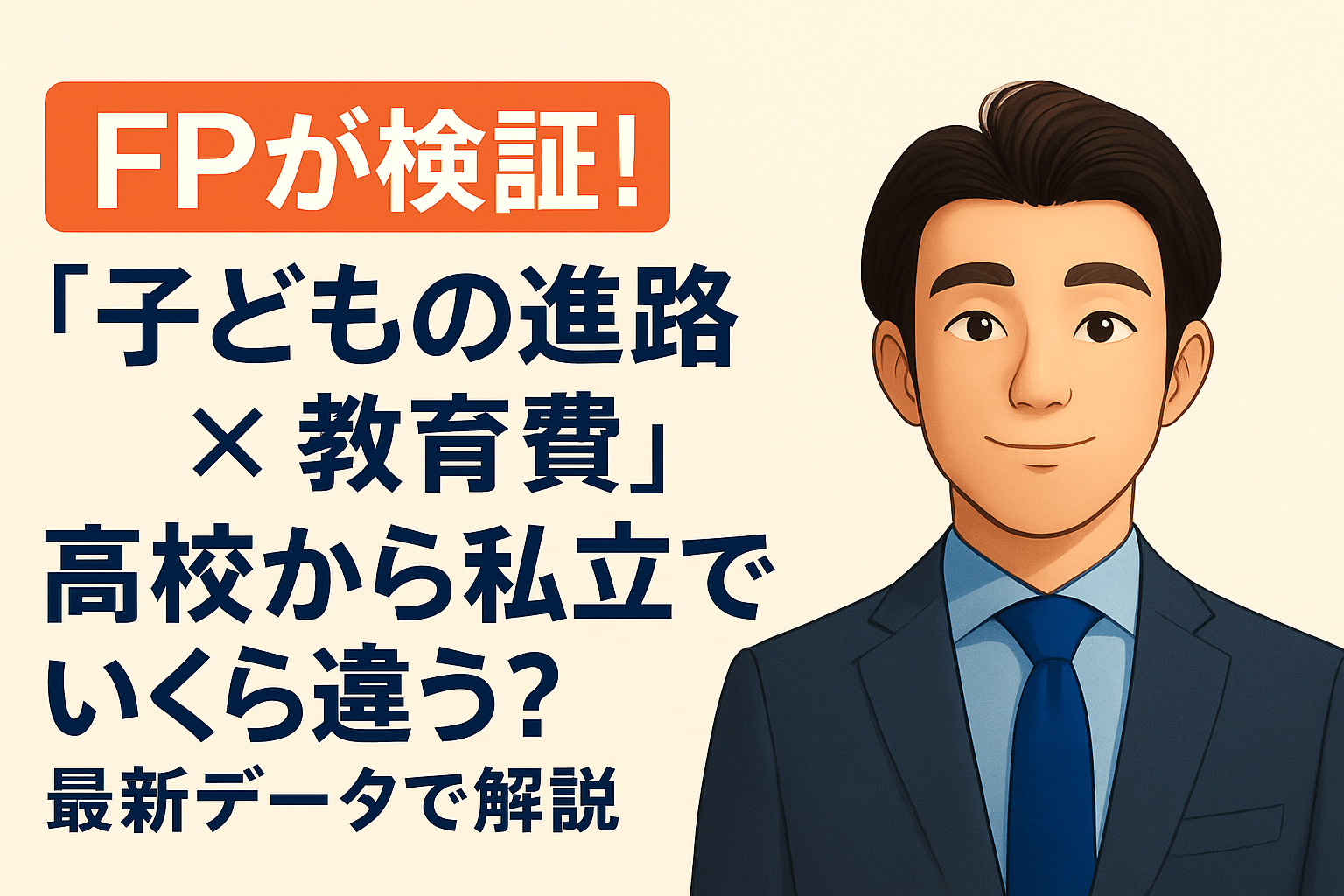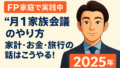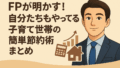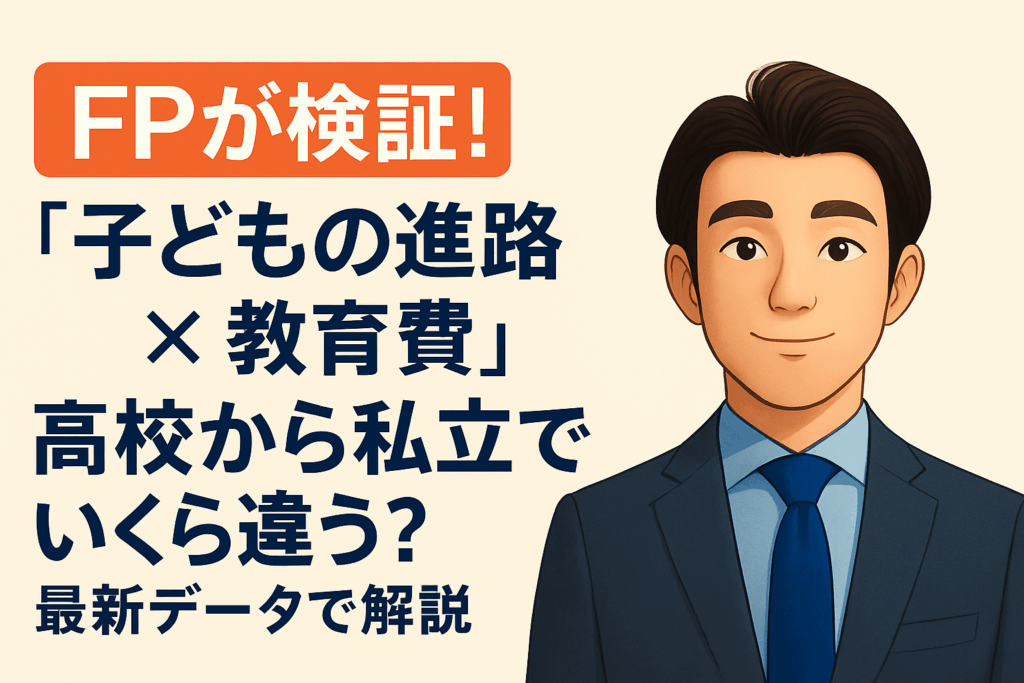
「中学までは公立、でも高校は私立でもいいかな?」――この一言が、家計に与えるインパクトは想像以上です。FP(ファイナンシャルプランナー)として延べ1,000世帯超の教育資金設計をしてきた立場から、最新相場とリアル家計データ、現場の“あるある”までまとめて公開します。
このブログでわかること
- 高校から私立にした場合に増える“本当の差額”(学費+周辺費用)
- 大学まで見通したルート別総額比較(公立→国公立/私立→私立文系/私立→私立理系)
- FP相談の現場で多い資金計画のつまずきと解決策(奨学金・就学支援金・積立の配分)
- 家計に無理なく備えるための「年齢別・月額積立シミュレーション」
まず把握すべきは“学費だけじゃない”という事実
比較表で語られがちなのは授業料中心の「学費」。しかし、実際に家計を圧迫するのは通学費・模試/受験料・部活費・端末代・寄付/施設費・昼食代などの“周辺費用”です。FP面談では、ここを見落として「想定外の赤字」が起きがちです。
| 費目 | 公立高校(年間目安) | 私立高校(年間目安) | 差の傾向 |
|---|---|---|---|
| 授業料・学校納付金 | 約45万円 | 約90〜110万円 | 大 |
| 通学定期・交通費 | 3〜8万円 | 5〜15万円 | 中 |
| 教材・タブレット等 | 1〜3万円 | 2〜7万円 | 中 |
| 部活・遠征・合宿 | 1〜5万円 | 2〜15万円 | 差が出やすい |
| 模試/検定・受験準備 | 1〜3万円 | 2〜4万円 | 小〜中 |
※筆者面談記録のレンジと公開相場からの概算。地域・学校・部活で上下します。
高校3年間の差額は?(FP算定の現実的レンジ)
授業料+周辺費用まで含めた総コストで見ると、
- 公立高校:年間 約55〜65万円 ⇒ 3年で 約165〜195万円
- 私立高校:年間 約110〜140万円 ⇒ 3年で 約330〜420万円
差額レンジ:3年で約160〜230万円。広告の数字(授業料のみ)よりも差が拡大しやすいのが実務の実感です。
大学まで見通すとどれくらい違う?(自宅通学モデル)
| 進路ルート | 高校3年 | 大学4年 | 合計額(高校+大学) |
|---|---|---|---|
| ①公立→国公立大 | 約180万円 | 約520〜560万円 | 約700〜740万円 |
| ②私立→私立文系 | 約360〜400万円 | 約680〜760万円 | 約1,040〜1,160万円 |
| ③私立→私立理系 | 約360〜400万円 | 約820〜950万円 | 約1,180〜1,350万円 |
高校から私立+私立大学理系まで進むと、公立→国公立と比べて総額でおおむね400〜600万円前後の差になるのが一般的なレンジです(自宅外・医歯薬はさらに加算)。
FP現場の“あるある”3例と処方箋
ケース1:特進合格で私立へ方針転換(子1)
- 当初:公立想定で準備額は高校〜大学で計750万円
- 変更後:私立特進+私立文系へ傾き、想定は1,050万円へ
処方箋:児童手当・学資をベースに、親名義のつみたてNISAを教育目的バケットへ再配分。高2から年40万円を安全資産へ段階的スイッチして“入学金ショック”を回避。
ケース2:兄公立×妹中高一貫私立(子2)
- 兄(公立→国公立):約720万円
- 妹(私立一貫→私立文系):約1,150万円
処方箋:兄の教育費ピーク時期と妹の入学時期が重なる年に注意。進学年の前々年から特別費バッファを月3万円積増し、不足分を一時的に国の教育ローンで橋渡し→入学後1年で繰上げ返済。
ケース3:授業料無償化の勘違い
高等学校就学支援金で「私立でも無料」と誤認。実際は世帯年収・学校納付金の構造で自己負担は残るケースが多数。
処方箋:“授業料”以外の納付金・施設費・教材費・指定品を事前確認。FP面談では学校パンフと家計簿を並べて年間現金必要額の月割り表を作成します。
年齢別・月額積立シミュレーション(利回り2.5%想定)
| 開始年齢 | 目標:高校〜大の教育費 1,000万円 | 毎月の積立目安 | FPワンポイント |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 18年後 | 約3.9万円/月 | 児童手当を全額投資バケットへ。学資は“安全資産枠”で併用 |
| 5歳 | 13年後 | 約5.5万円/月 | ボーナス月に加速。親のつみたてNISA満枠×2口座が効く |
| 10歳 | 8年後 | 約8.6万円/月 | 高校入学金に備え中3から段階的に守りへ |
入学ピーク前にリスク資産→現金・短期国債へスイッチする「出口戦略」を設計しておくと、直前の相場下落に巻き込まれにくくなります。
奨学金・支援制度・税制の押さえどころ
- 高等学校就学支援金:世帯収入に応じて授業料相当を軽減。学校納付金の全てがゼロになるわけではない点に注意。
- 授業料減免・給付型奨学金:私立は校独自制度が手厚いことも。オープンキャンパスで要確認。
- 国の教育ローン:入学金支払いの橋渡しとして有効。額と返済年数は保守的に。
- NISAの活用:親名義のつみたて枠で教育用バケットを作り、目的別に口座を分けるとブレにくい。
家計が無理しないための設計フレーム(FPテンプレ)
- ルート仮置き(公立/私立×文理)を2〜3案作る
- 年次キャッシュフローに「入学金・納付金・模試/受験・通学費」をプロット
- 目的別口座(教育・老後・旅行)を分け、自動積立に
- 出口戦略(中3・高2・浪人想定)の換金ルールを明文化
- 年1回の家族会議で前提を更新(成績・志望・家計の変動)
まとめ|“将来の選択肢”と“家計の持続可能性”のバランスを
高校から私立を選ぶ価値は、学習環境・進学実績・手厚い指導など、確かに大きい。一方で家計の現実を無視すれば、大学進学の選択肢を狭めることもあります。だからこそ、高校の選択は大学まで含めた「総額」と「キャッシュフロー」で判断するのがFP的な正解です。
数十万円ではなく、数百万円単位の差が生まれる決断。今日の情報が、あなたのご家庭の最適解を選ぶ助けになれば幸いです。